勤務医として働く医師にとって、開業するかどうかは大きな悩みのひとつです。
年齢やキャリア、家族の状況、資金、地域の医療ニーズなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。
本記事では、勤務医が開業を考える最適なタイミング、近年の開業動向、クリニック経営を取り巻く環境、勤務医との違い、さらに支援制度や事例までを整理して解説します。

クリニック経営の環境を知っておくことで、「開業するかどうか」の判断をしやすくなります!ぜひ参考にしてみてください。
開業のタイミングをどう考えるか

開業の時期は人によって異なりますが、大きく分けると二つのタイプがあります。
一つは30代前半など、比較的若いうちに開業するケース。
もう一つは40代に十分な経験を積んでから開業するケースです。
若いうちに開業すると、金融機関から資金を調達しやすく、購入した設備を長く活用できます。
体力的にも余裕があり、往診や長時間診療にも柔軟に対応できるでしょう。
一方で、経営的・指導者的な経験が乏しく、資金繰りやスタッフ管理などに不安が残る点が課題です。
経験を積んでからの開業には、患者対応や経営判断に自信を持って臨める利点があります。
高度な医療技術や専門性を発揮でき、勤務医時代に築いた人脈も大きな武器になります。
ただし、体力的な負担が増えたり、タイミングを逃してしまう可能性もあります。
実際のデータでは、新規開業医の平均年齢は40歳前後です。
日本医師会(2009年)の調査では41.3歳、日本政策金融公庫(2020年度)では43.7歳という結果でした。
この年代がボリュームゾーンではあるものの、必ずしも「40代がベスト」とは限りません。
若いうちの開業にも大きなメリットがあるため、経験を積むことだけを重視しすぎず、場合によっては早めの決断も選択肢になります。
30代で開業を目指す場合は、勤務医として経験を積みながら、経営の知識や事業計画の立て方を学びましょう。
自己資金の準備や金融機関との関係づくりも欠かせません。
勤務先で経営の仕組みを観察し、人脈を広げておくことも大きな財産になります。
結局のところ、開業の「適齢期」は一概には言えません。
キャリア、家族、経済状況、地域の需要などを総合的に見て判断することが大切です。
開業件数のトレンドと背景

厚生労働省の統計によると、開業医の割合は年々低下しています。
2000年には開業医の割合が約31%でしたが、2020年には24%に下がりました。
医師数は増えているのに、開業医の増加は緩やかだからです。
勤務医志向が強まっていることが数字にも表れています。
1990年代後半から2010年代にかけて、医師数は大幅に増加しました。
しかし診療所の開設者数はほぼ横ばい。
開業志向が下がっている背景には、患者数の減少や競争激化、在宅医療の負担増などがあります。
また、勤務医の働き方改革が進み、短時間勤務や当直免除など柔軟な働き方が選べるようになったことも理由の一つです。
現在のクリニック経営環境
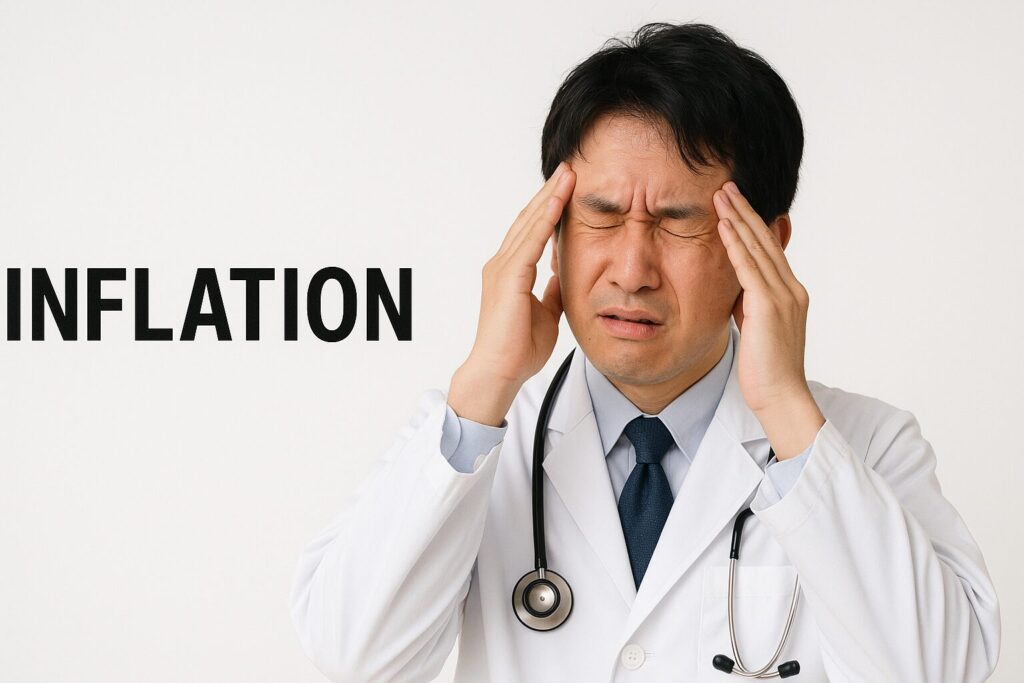
ここ数年で、医療機関を取り巻く環境は大きく変わりました。
物価上昇や人件費の高騰、スタッフ不足などがクリニック経営を圧迫しています。
特に2022年以降の電気・ガス料金や医療材料費の値上がりは深刻です。
約9割の医療機関が光熱費の負担増を実感しており、2割近くは20%以上の上昇を報告しています。
一方で、診療報酬は2年ごとの改定にとどまり、急な物価高には追いついていません。
2023年改定後、7割以上のクリニックが「収入が減った」と回答しています。
さらに看護師やスタッフの採用競争が激しく、給与引き上げや高額な人材紹介料の支払いが避けられない状況です。
電子カルテ導入やオンライン診療対応にもコストがかかり、補助金を活用しても負担は軽くありません。
この「物価高」「人件費増」「デジタル化対応」の三重負担が、クリニックの経営を直撃しています。
光熱費・材料費・薬剤費・人件費の上昇分を「診療報酬でカバーできない」と答えたクリニックは約9割に上り、経営悪化を訴える声が増えています。
こうした中で新規開業を成功させるには、初期投資の見積もりと経営シミュレーションを入念に行い、十分な資金的余裕を確保しておくことが欠かせません。
開業医と勤務医の違い

まず収入面では、開業医は勤務医の約2倍の収入が見込めます。厚労省の調査によると、勤務医の平均年収は約1,488万円、開業医は約2,748万円でした。
もちろん診療科や経営状況によって幅はありますが、経営が安定すれば大きなリターンが得られる職種です。
働き方の自由度も大きな違いです。
勤務医は当直や緊急対応などで長時間労働になりがちですが、開業医は自分で診療時間や休日を調整できます。
一方で、開業医は経営者でもあります。
診療に加えてスタッフ管理や経理、広報活動なども担わなければなりません。
開業当初は勤務医時代より多忙になるケースも多く、「自由」は努力の上に成り立っています。
また、経営リスクも自分で背負うことになります。
患者数の減少や競合の出現、予期せぬ設備更新などが直接収入に影響します。
ただし、クリニックの倒産率はわずか0.75%。
多くの開業医は堅実に経営を続けています。十分な準備と努力があれば、過度に恐れる必要はありません。
支援制度と成功・失敗事例

開業支援の制度は多岐にわたります。
日本政策金融公庫や民間銀行の医療ローンをはじめ、IT導入補助金やものづくり補助金、事業再構築補助金などの公的制度も活用可能です。
地方自治体では、医師不足地域で開業する医師に数千万円規模の補助金を出す例もあります。
静岡県牧之原市では最大5,000万円、勤務実績に応じてさらに加算される制度もあります。
また、民間の開業支援サービスや医療モール企業も増えており、物件探しから広告戦略までトータルでサポートを受けられます。
初めての開業で不安な場合は、専門家とチームを組むのも効果的です。
成功例では、地域ニーズに合った戦略的な開業が共通点です。
高齢化地域で訪問診療に力を入れたクリニックや、競合の少ない診療科を選んだケースは安定した経営を実現しています。
反対に失敗例では、立地の誤りや過大投資、資金繰りの甘さが原因となっています。
開業前の事業計画を第三者の目でチェックしてもらうことが重要です。
まとめ
勤務医が開業を考える際は、年齢やキャリアだけでなく、家族、地域、資金、経営環境といった多角的な視点で判断することが大切です。
準備には時間と労力がかかりますが、支援制度や専門家をうまく活用すれば、リスクを抑えながら理想の医療を実現できます。
開業には勇気が要りますが、得られるやりがいや自由度も大きな魅力です。
自分の理想とする医療を形にするチャンスとして、最善のタイミングを見極めて一歩を踏み出してください。
地域の患者さんから求められる、充実したクリニック経営がきっと待っています。
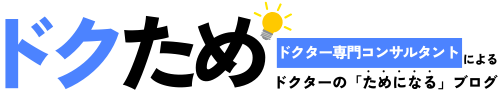
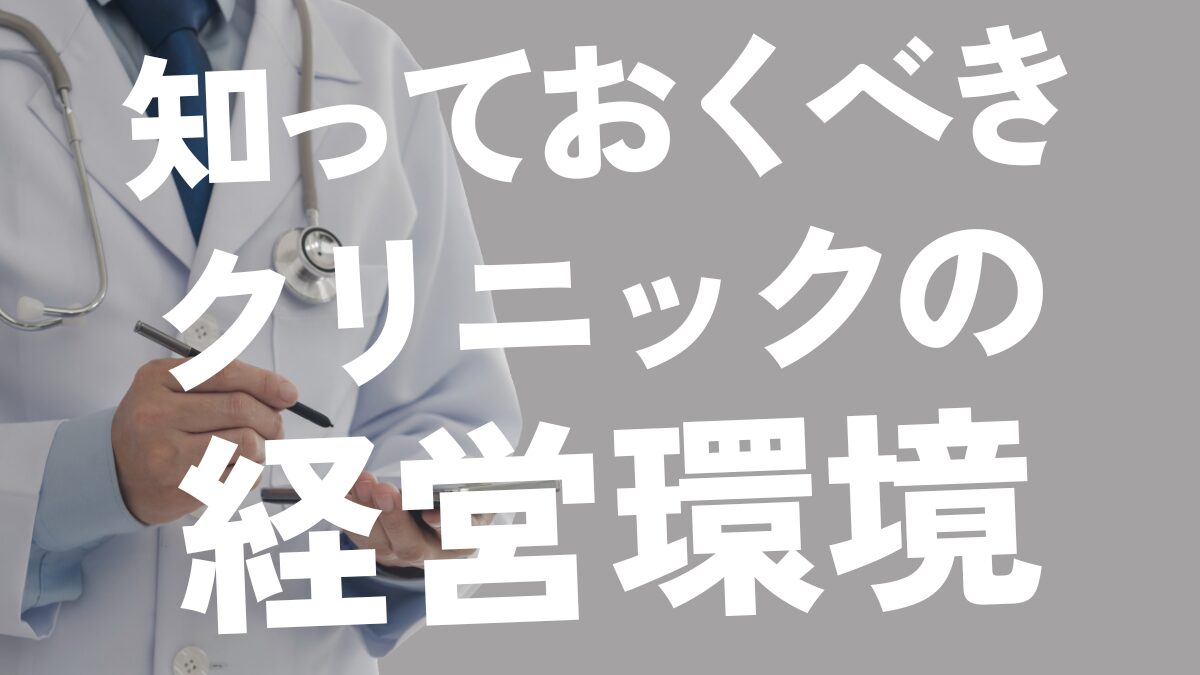
コメント